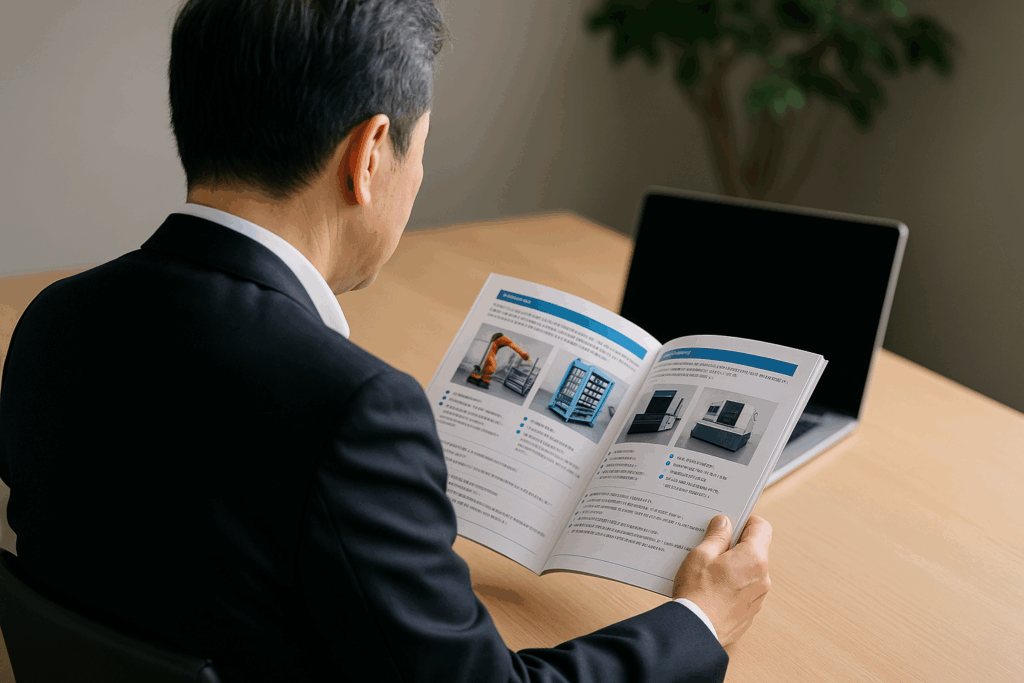本ページは2025年9月19日発表の第4回公募要領に基づき作成しています。要領は改訂される場合があります。申請前に必ず事務局サイト掲載の最新版をご確認ください。
本記事では、各章の冒頭に「その章でわかること」を簡単にまとめています。まずは冒頭まとめをチェックして、自分に必要な内容を見極めたうえで、詳しく知りたい部分を本文でご確認いただくのがおすすめです。
1. 省力化投資補助金(一般型)とは
人手不足や生産性低下に悩む中小企業を対象に、IoT・AI・ロボット等を活用した省力化設備の導入を国が支援する制度です。生産性向上と賃上げを両立することを目指します。
制度の概要
省力化投資補助金(一般型)は、中小企業・小規模事業者が直面する深刻な人手不足に対応するための国の補助制度です。
IoT・AI・ロボット・センサーなどのデジタル技術を活用した専用(オーダーメイド)設備を導入することで、作業の省力化・自動化を進め、生産性向上と賃上げの好循環を生み出すことを目的としています。
省力化投資補助金(一般型)の特徴は、同じ制度内の「カタログ注文型」と異なり、各社の業務プロセスに合わせて設計・構築する個社最適なシステム・設備導入を対象とする点です。
💡省力化投資補助金(カタログ注文型)について知りたい方はこちらをご覧ください↓
本制度で想定する課題と解決アプローチ
- 現場の人手不足・長時間労働・属人化
- 受注増や多品種少量化への対応遅れ
➡ 個社の業務要件に合わせたシステム構築や機械装置の導入により、
作業工数の削減・品質の安定化・業務の可視化 を実現します。
主な用語の説明
- オーダーメイド設備
IoT・AI・ロボット・センサー等を活用し、外部のシステムインテグレーター等と連携して、自社の業務に合わせて設計される専用設備やシステムのことです。 - 省力化
既存業務で発生している作業時間(工数)を、恒常的に削減することを指します。 - 省力化指数
導入前と導入後で削減できた業務時間の差を数値化した指標です。 - 付加価値額/労働生産性
経営成果を測るための基本指標。補助事業の成果確認で活用されます。 - 投資回収期間
削減できた工数や増加した付加価値を踏まえて、投資した金額を回収するまでの目安期間です。
2. 補助対象となる事業者
本補助金は、日本国内で事業を営む中小企業、小規模事業者、一定の中堅企業や組合等が対象です。業種ごとに資本金や従業員数の基準が定められており、個人事業主も申請できます。
共通の前提要件
国内要件:日本国内に本社があり、補助設備を設置する事業実施場所も国内であること
事業形態に応じた要件:
- 法人の場合:応募時点で法人登記が完了し、法人番号が国税庁サイトに公表されていること
- 個人事業主の場合:国内で事業を営んでいること
対象区分の早見表
A. 中小企業者(組合関連以外)
資本金または常勤従業員数のいずれかが基準内であれば対象となります。
| 業種 | 資本金(上限) | 常勤従業員数(上限) |
|---|---|---|
| 製造・建設・運輸 | 3億円 | 300人 |
| 卸売 | 1億円 | 100人 |
| サービス(※ソフトウェア・情報処理・旅館を除く) | 5,000万円 | 100人 |
| 小売 | 5,000万円 | 50人 |
| ゴム製品製造(※自動車/航空機用タイヤ等を除く) | 3億円 | 900人 |
| ソフトウェア/情報処理 | 3億円 | 300人 |
| 旅館 | 5,000万円 | 200人 |
| その他の業種 | 3億円 | 300人 |
B. 小規模企業者・小規模事業者
従業員数で判断されます。
| 区分 | 常勤従業員数(上限) |
|---|---|
| 製造業その他/宿泊業/娯楽業 | 20人以下 |
| 卸売・小売・サービス業 | 5人以下 |
C. 特定事業者の一部(※資本金10億円未満、いわゆる中堅企業の一部を含む)
資本金(出資総額)が10億円未満で、かつ従業員数が業種ごとの上限以内であれば対象になります。
この区分には、いわゆる 中堅企業の一部 も含まれます。
| 業種 | 常勤従業員数(上限) |
|---|---|
| 製造・建設・運輸 | 500人 |
| 卸売 | 400人 |
| サービス/小売(※ソフトウェア・情報処理・旅館を除く) | 300人 |
| その他の業種 | 500人 |
D. 中小企業者(組合関連)
次のような各種組合等も対象です。
- 企業組合、協業組合
- 事業協同組合/小組合/連合会
- 商工組合/商店街振興組合および連合会
- 水産加工業協同組合/生活衛生同業組合 等
- 酒造組合・酒販組合、内航海運組合 等
申請にあたっての注意点
- みなし同一法人の扱い
親会社が議決権の50%超を保有する子会社など、同一グループとみなされる場合は、1社のみ申請可能です。 - 小規模の扱い
従業員数が小規模事業者の定義から外れると、補助率が変更になる場合があります。
3. 補助対象経費と補助額
補助金は「50万円以上の機械装置を1点以上導入」が必須条件です。関連経費も対象になりますが条件あり。補助額は従業員数と補助率で決まり、大幅賃上げの取組みには特例加算もあります。
補助対象となる主な経費
必須経費
- 単価50万円(税抜)以上の機械装置・システムを1点以上導入することが前提です。
対象となる経費の例
- 機械装置・システム構築費(工具・器具、専用ソフトウェア、情報システムの購入・構築・据付を含む)
- ※ただし船舶・航空機・車両は対象外
- 運搬費
- 技術導入費
- 知的財産権等関連経費
- 外注費(補助事業に直接必要なものに限る)
- 専門家経費(導入支援や効果検証など)
- クラウドサービス利用費(補助事業に必要な期間分のみ)
- 機械装置以外の経費には、補助対象経費合計に対する上限割合が設定されています。
- いずれの経費も、交付決定日以降に契約・支払いを行い、事業実施期間内に完了すること が条件です。
補助対象外となる主な経費
以下は補助対象になりません。
- 交付決定前の契約・着手(いわゆる「事前着手」)
- 既存設備の改修のみ
- パッケージ/汎用ソフトの購入・設定のみ
- 通常業務の代行費
- 船舶・航空機・車両の購入
補助額と補助率
補助額は 従業員数ごとの上限額 と 補助率 により決まります。
従業員数ごとの上限額(基本)
| 常勤従業員数 | 上限額 |
|---|---|
| 5人以下 | 750万円 |
| 6~20人 | 1,500万円 |
| 21~50人 | 3,000万円 |
| 51~100人 | 5,000万円 |
| 101人以上 | 8,000万円 |
大幅賃上げに取り組む場合の特例(上限額の上乗せ)
「大幅賃上げ」に取り組む場合、従業員数に応じて上限額を加算できます。
ただし、最低賃金引上げ特例の適用者・上限未達事業者・再生事業者・常勤従業員ゼロ の場合は対象外です。
| 常勤従業員数 | 加算額 | 特例適用時の上限額 |
|---|---|---|
| 5人以下 | +250万円 | 1,000万円 |
| 6~20人 | +500万円 | 2,000万円 |
| 21~50人 | +1,000万円 | 4,000万円 |
| 51~100人 | +1,500万円 | 6,500万円 |
| 101人以上 | +2,000万円 | 1億円 |
補助率
| 区分 | ~1,500万円部分 | 1,500万円超部分 |
|---|---|---|
| 中小企業 | 1/2(特例時 2/3) | 1/3 |
| 小規模企業者・小規模事業者/再生事業者 | 2/3 | 1/3 |
※「最低賃金引上げ」に取り組む場合、中小企業の~1,500万円部分は 補助率2/3 に引き上げられます。
4. 公募スケジュール
省力化投資補助金(一般型)は年間3~4回の公募が予定されています。公募開始から採択、交付申請、事業実施、実績報告、補助金支払いまでの流れを理解しておきましょう。
第4回公募期間:
2025年11月4日(火)10:00~2025年11月27日(木)17:00
大まかなスケジュール
一般的な流れは以下のとおりです。ただし実際のスケジュールは回ごとに異なるため、必ず最新の公募要領をご確認ください。
- 公募開始:事務局サイトで要領公開とともにスタート
- 申請受付:約1〜2か月間、原則電子申請
- 審査・採択発表:締切から1〜2か月後に公表
- 交付申請・事業開始:採択発表から原則2か月以内
- 事業実施期間:交付決定日から18か月以内(ただし採択発表日から20か月以内)
- 実績報告・補助金請求:事業完了後に報告書提出・検査を経て支払い
過去の実施状況(参考)
- 2025年 第1回:公募開始 1/30 → 採択発表 6/16
- 2025年 第2回:公募開始 4/15 → 採択発表 8/8
- 2025年 第3回:公募開始 6/27 → 採択発表 11月下旬予定
- 2025年 第4回:最新要領に基づき公募中
補足:「省力化投資補助金(カタログ注文型)」は2024年以降、随時受付 に移行しており、一般型とは運用スケジュールが異なります。
5. 申請要件
申請できるのは国内の中小企業・小規模事業者・一部の中堅企業等です。必須要件を満たすことが前提で、加点要件や特例要件を満たすと採択評価や補助率が変わります。第4回では最低賃金関連の加点・特例に新条件が追加されています。
対象者
- 日本国内に本社または事業所を有する中小企業・小規模事業者・一部の中堅企業等
- 詳細な資本金・従業員数の基準、組合等の取扱いについては第2章を参照
必須要件チェックリスト
申請を検討する際は、以下の要件をすべて満たしているか確認してください。
□ 日本国内に本社または事業所がある
□ 中小企業基本法に定める資本金・従業員数の基準に合致している
□ 単価50万円以上の機械装置を1点以上導入する
□ 生産・業務プロセスやサービス提供方法の省力化に該当する取り組みである
□ ICT/IoT/AI/ロボット等を活用した専用設備(オーダーメイド設備等)の導入計画である
□ 補助対象経費は交付決定後の契約・支払いで、期間内に発注・納品・検収・支払を完了できる
□ 実施期間は交付決定日から18か月以内(採択発表日から20か月以内)である
□ 賃上げ・生産性向上に関する必達目標を設定できる
□ 電子申請(jGrants)で申請し、GビズIDプライムを取得済み
賃上げ・生産性向上に関する必達目標(補足)
申請時に会社全体として以下を設定し、事後に達成状況を報告します。
- 労働生産性:年平均成長率 +4.0%以上
- 以下のいずれかを達成
- 1人当たり給与支給総額の年平均成長率が、事業実施都道府県の最低賃金の直近5年平均上昇率以上
- 給与支給総額の年平均成長率 +2.0%以上
- 事業場内最低賃金:事業実施都道府県の最低賃金 +30円以上
- 従業員21名以上の事業者は「一般事業主行動計画」の策定・公表が必要
「最低賃金引上げ特例」対象者は 1. 労働生産性、2. 給与総額、4. 行動計画 の3つを満たせば可。
加点要件(審査で有利になる条件)
- <NEW>地域別最低賃金引上げ加点(第4回より追加)
2024年10月~2025年9月に、地域別最低賃金以上かつ2025年度改定最低賃金未満の従業員が全体の30%以上となる月が3か月以上ある場合 - <NEW>事業場内最低賃金引上げ加点(第4回より条件が明確化)
2025年7月時点と直近の事業場内最低賃金を比較して 63円以上 引き上げている場合 - その他、えるぼし認定、くるみん認定 等
特例要件
- 大幅賃上げ特例
従業員数に応じて補助上限額を加算可能
※ 最低賃金特例の適用者・上限未達事業者・再生事業者・常勤従業員ゼロは対象外 - 最低賃金引上げ特例
一部の必須要件が緩和され、中小企業の補助率が引き上げられる場合あり
6. 事業計画書作成のポイント
事業計画書は採択を左右する最重要書類です。審査員が評価する観点を踏まえて、根拠を明確に、読みやすく整理することが成功のカギです。
本章では、本制度ならではの重点ポイントに絞って解説します。
「読み手(審査員)が評価しやすい」形に寄せて、何を書くべきかとどう書くと伝わるかを整理しました。
補助金申請に必要な事業計画書の書き方の基本が知りたい方は、こちらもご覧ください↓
審査の観点(評価の4本柱+全社成果)
事務局が特に重視する「審査の4本柱」は以下のとおりです。
- 省力化指数:工数削減効果の大きさ
- 投資回収期間:費用対効果の妥当性
- 付加価値額・労働生産性・賃上げ:経営全体への波及効果
- オーダーメイド設備の妥当性:専用設計の必然性
あわせて、全社的な数値計画(労働生産性+4.0%や賃上げ目標など)の達成可能性も評価対象になります。
章立て・見出しもこの順で揃えると読みやすくなるでしょう。
書き方のポイント
省力化指数
定義式:〔導入前工数 − 導入後工数〕 ÷ 導入前工数
書き方:
- 削減対象とする工程・作業を明示し、「どの作業を何分減らすのか」を具体的に書く
- Before/After の工数テーブルを作成し、見える化する
- 新規出店や将来の業務拡大を見込む場合は、将来の削減時間も組み込んでよい
- カタログ注文型に類似する設備カテゴリがあれば明記すると審査で考慮されやすい
投資回収期間
定義式:投資額 ÷(削減工数×人件費単価 + 増加付加価値額)
書き方:
- 「人件費単価」の根拠(例:賃金台帳、給与明細)を明記する
- 「増加付加価値額」は粗利や加工高などの積算根拠を添える
- 試算の前提条件(稼働率・処理量・不良率など)も明文化する
- 数式+根拠資料をセットで示すことが重要
付加価値・生産性・賃上げ
定義:
- 付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
- 労働生産性=付加価値額 ÷ 労働者数
書き方:
- 会社全体の事業計画を表で整理し、労働生産性・給与総額・賃上げ目標を一括で示す
- 各数値には算出根拠を付す(単価×数量、人件費の積算など)
- これらは採択後、毎年の効果報告で検証されるため、無理のない実現可能な計画とすること
オーダーメイド設備の妥当性
定義:自社の工程に合わせて設計された専用設備(ICT/IoT/AI/ロボット/センサー等を活用)
書き方:
- レイアウト、段取り、安全対策、周辺機器とのインターフェース(I/F)を具体的に記載
- 「汎用品では代替できない理由」と「導入する構成機器の選定理由」を論理的に説明する
- カタログ注文型に該当する場合は、カテゴリ名を明記する
ストーリーライン:会社全体への波及まで
事業計画書は、次の3つの段階に分けて書くと読み手にとって分かりやすくなります。
- 取り組みの具体と全社目標との整合
現状の課題 → 導入必然性 → 取得資産(型番・数量・時期) → 省力化効果 → スケジュール - 将来の展望
削減した労働力をどこに再配分し、どんな付加価値を生むかを簡潔に記載 - 会社全体の数値計画
労働生産性・給与総額・賃上げ等の目標を、計算式と根拠を添えて表で提示(省力化指数・投資回収・付加価値等も同様)
その他の必須・推奨事項
必須
- 取得資産一覧(単価50万円以上):名称・型番・数量・単価・計上区分・設置場所
- 実施場所の特定(住所や配置イメージ図)
推奨
- システム構築概要(該当する場合:目的/機能範囲/成果物)
- スケジュール(交付決定後→発注→納品→検収→支払→実績報告)
- 体制(申請者の責任者・実務担当、ベンダー側の窓口)
- 価格妥当性(見積根拠・選定理由の概要)
- 添付資料リスト(見積書/仕様書/図面/カタログ/レイアウト図など)
事業計画書チェックリスト(簡易診断用)
省力化投資補助金(一般型)申請用の事業計画書の妥当性を簡易に診断するためのチェックリストです。ぜひご活用ください。
A. 技術評価(審査の4本柱)
□ 省力化指数:前提と導入前後の工数が明確で、効果が十分
□ 投資回収期間:算定式と前提が妥当で、短期間で回収可能
□ 付加価値額の増加:積算根拠(単価・数量・粗利など)が具体的
□ オーダーメイド設備の妥当性:専用設計の必要性が論理的で、汎用品では代替不可
B. 経営成果・賃上げ(基本要件の実現性)
□ 労働生産性:年平均+4.0%以上の目標と根拠を提示
□ 給与:①1人当たり給与=最低賃金5年平均上昇率以上 または ②給与総額=年平均+2.0%以上
□ 事業場内最低賃金:地域最低賃金+30円を織り込み
□ 削減した工数の再配分先(高付加価値業務や新サービス)が具体
C. 実現可能性(計画・体制・資金)
□ スケジュール:期間内に全工程を完了できる計画
□ 体制:責任者・担当者・ベンダー窓口を明記
□ 資金計画:自己資金・借入の裏付けがある
□ リスク対策:調達遅延・開発難易度・設置工事等への対策を記載
D. 適格性・コンプライアンス
□ 対象事業・対象経費を満たし、対象外経費を含まない
□ 支出ルール:交付決定後の契約・支払いのみ
□ 他補助金との重複受給がない
□ 外部支援の透明化(支援者名・報酬・期間を明示可能)
E. 根拠・図表(説得力)
□ 工数テーブル:Before/After工数・処理量を表で可視化
□ 取得資産一覧:型番・数量・単価・設置場所を一覧化
□ 配置・工程図:レイアウトや動線を図示
□ 見積根拠:概算見積や単価の根拠を提示
F. 申請書の読みやすさ
□ 章立て:審査の4本柱→基本要件→体制・資金の順で整合
□ 用語・数式:定義・単位を統一し、本文・表・添付の数字も一致
□ 要約:冒頭に“ねらい・効果・投資回収”のサマリーがある
G. 特例・加点(該当時)
□ 大幅賃上げ特例:追加要件を満たしている
□ 最低賃金引上げ特例:条件を確認し、必要な記載を反映
□ 地域別最低賃金引上げ加点(第4回より追加):2024年10月~2025年9月の間に、地域別最低賃金以上かつ改定後最低賃金未満の従業員が全体の30%以上となる月が3か月以上ある
□ 事業場内最低賃金引上げ加点(第4回で要件明確化):2025年7月時点と直近の比較で、事業場内最低賃金を63円以上引き上げている
□ その他加点:えるぼし認定・くるみん認定など
7. 申請の流れ
申請は電子申請システム「jGrants」で行います。事前準備から実績報告までの流れを理解しておくことで、スケジュール遅延や書類不備による不採択リスクを避けられます。
申請から補助金受給までの流れは、大きく次の7ステップに分かれます。
- 事前準備
- 申請書類の作成
- 電子申請(jGrantsでの提出)
- 審査・採択結果の公表
- 交付申請・交付決定
- 事業実施
- 実績報告・補助金請求
以下でそれぞれを詳しく解説します。
Step 1. 事前準備
- GビズIDプライムの取得(発行に時間がかかるため早めに対応)
- 公募要領・申請様式の入手:最新版を公式サイトからダウンロードし、条件や必要書類を確認
Step 2. 申請書類の作成
事業計画書など必要書類を準備し、申請様式に沿って入力します。
申請内容は、要件や審査項目に沿って作成することが重要です。
必要書類(申請時)
共通(必須)
- 事業計画書(電子申請フォーム一式に沿って作成・提出)
法人の場合の主な添付書類
- 履歴事項全部証明書(発行から3か月以内)
- 納税証明書(その2)直近3期分
- 法人事業概況説明書
- 【指定様式】役員名簿
- 【指定様式】株主・出資者名簿
法人の場合の主な添付書類
- 確定申告書(第一表)の控え
- 納税証明書(その2)直近1年分
- 所得税青色申告決算書 または 白色申告収支内訳書
そのほか、状況に応じて追加書類が必要となる場合あり(詳細は公募要領参照)
Step 3. 電子申請(jGrants)
- jGrantsにログインし、申請フォーム入力・書類添付・期限内送信
- 添付ファイルの誤りやパスワード設定があると審査対象外になるため注意
Step 4. 審査・採択結果の公表
- 締切後、審査を経て採択結果が公式サイトで公開
- 法人番号・事業者名・所在地(市区町村)・事業計画名などが公表されます
- 採択後は交付申請に進みます
Step 5. 交付申請・交付決定
- 採択から原則2か月以内に交付申請(期限が難しい場合は事前に事務局へ相談)
- 交付決定通知後に事業開始可能
- この段階で価格妥当性資料が必要
- 機械装置(50万円以上):相見積
- システム関連:仕様書+積算根拠
Step 6. 事業実施
- 交付決定後に契約・発注・支払いを行い、交付決定から18か月以内(採択発表から最長20か月以内)に完了
- 契約 → 納品 → 検収 → 支払 → 実績報告の流れを期限内に完結
- 支払いは銀行振込で確認(現金・手形は不可。原則クレジットカード不可)
Step 7. 実績報告・補助金請求
- 事業完了日から30日以内、または完了期限日のいずれか早い日までに実績報告書を提出
- 事務局の検査を経て補助金が精算払で交付
- 補助金受給後も交付年度終了後5年間は効果報告が必要(未提出・虚偽は返還対象)
8. 採択の傾向とポイント
採択されやすい計画には共通点があります。公開データから分かる業種や金額帯の傾向と、審査員に評価される要素を整理しました。採択率の動向も確認しておきましょう。
採択されやすい事業の特徴
- 審査の4本柱が強い計画
- 工程別の省力化効果が明確(省力化指数が高い)
- 投資回収が早く、算定式と前提に妥当性がある
- 付加価値額の伸びが数字で裏付けられている
- 専用設計の妥当性が論理的に示されている
※審査の4本柱が強い計画の書き方は第6章をご参照ください。
- 分野の傾向
- 第1回採択では製造業が約62%、建設業が約11%と多め
- ただし卸売・小売・サービスなど幅広い業種からも採択実績あり
- 金額帯の傾向
- 採択者の申請額は1,500~1,750万円が最多
- 上限近くを申請する事例が目立ちます
- 事例の共通点
- ロボット × 3Dスキャナなどデジタル技術を組み合わせた専用ライン化が多い
- 技能依存やヒューマンエラーを抑える設計が評価されやすい
採択率の傾向
- 2025年・第1回:申請 1,809件/採択 1,240件 → 約 68.5%
- 2025年・第2回:申請 1,160件/採択 707件 → 約 60.9%
初回は高めの採択率でしたが、第2回では6割程度に低下。
今後は応募件数の増加に伴い、緩やかな低下も見込まれます。
採択率を高めるためのポイント
採択データの傾向から見ると、次の点を押さえた計画が有利になります。詳細は第6章で解説しています。
- 工程別の工数削減効果を表や数式で明示
- 投資回収の算定式と前提条件を根拠付きで提示
- 専用設計の必然性を図解で説明
- 対象外経費を計画段階で除外
- 全社目標(生産性+賃上げ)との整合性を確保
9. 採択後の流れと義務
採択後は交付申請から事業実施・実績報告・効果報告へと進みます。補助金を受け取るには、資産管理や保険加入などの義務を守る必要があり、違反時は返還リスクもあります。
採択後の主な流れ
- 交付申請・交付決定
- 採択後2か月以内に交付申請を行います。
- 経費内容や価格妥当性を精査(50万円以上の設備は相見積、システムは仕様書+積算根拠が必要)。
- 交付決定通知後に契約・発注・支払いが可能になります。
- 事業実施(現地確認あり)
- 交付決定後に事業着手。
- 実施期間は交付決定日から18か月以内(採択発表日から最長20か月以内)。
- 事務局や中小機構による現地調査で設備・証憑を確認。確認できない経費は対象外です。
- 実績報告
- 事業完了後、納品・検収・支払い等の証憑を揃えて提出。
- 保険加入証明書類も提出対象です。
- 補助金の精算・支払
- 実績報告の検査後、補助金額が確定し、精算払で交付されます。
- 効果報告(毎年度)
- 事業計画期間(3〜5年)の各年度で、生産性・給与等の達成状況を報告。
- 年平均成長率で評価され、未達の場合は返還や減点措置の対象となることがあります。
採択後に守るべき義務
- 財産の管理・処分制限
- 取得資産は補助金適正化法に基づき、売却・転用・廃棄に制限。
- 違反時は残存簿価等の返還が必要です。
- 保険加入義務(原則必須)
- 導入資産には原則必ず保険または共済(付保割合50%以上)に加入する必要があります。
- 実績報告時に証明書類を提出します。
注意点
- 加点要件の未達ペナルティ
- 賃上げ等の加点を申請して未達だった場合、その報告から18か月間は次回公募や他制度申請で大幅減点となります(正当な理由がある場合を除く)。
- 義務違反時の措置
- 不適切対応・虚偽報告・資産管理不備があった場合は、交付決定取消・返還・不正内容の公表など厳しい措置が科されます。
10. 注意点
申請・実施・報告の各段階で誤りや不備があると、不採択や返還リスクにつながります。特に「設備投資必須」「対象外経費」「交付決定前着手」には注意が必要です。
👉 この章は、他の章で触れた要点を「落とし穴」という観点で再整理しています。
詳細は他章(第3章、第7章、第9章など)とあわせてご確認ください。
設備投資が必須
- 単価50万円(税抜)以上の機械装置等を1点以上導入することが前提。
- 納品・検収・管理まで完了して初めて対象となります。
- システム構築費は、交付申請時に仕様書・積算根拠を添付する必要があります。
👉 詳しくは第3章をご覧ください。
契約・支払いのルール
- 交付決定前の契約・支払いはすべて対象外。
- 支払いは銀行振込で確認します(現金・手形は不可、クレジットカードは原則不可)。
- やむを得ない場合は必ず事前に事務局へ相談してください。
電子申請の留意点
- 申請はjGrantsによる電子申請のみ。
- GビズIDプライムが必須で、発行に時間がかかるため早めの取得を。
- 添付ファイルの場所やパスワード設定の誤りは審査不可の原因になります。
👉 申請手順の全体像は第7章を参照してください。
補助対象外の典型例
以下はよくある対象外ケースです。計画段階で排除しましょう。
- パッケージ/汎用ソフトの購入・設定のみ
- 既存システムのバージョンアップや改修のみ
- 主課題の丸投げ外注
- 長期賃貸を目的とする導入
効果報告とペナルティ
- 生産性・賃上げなどの必達目標は、事業計画期間中(3~5年)の効果報告で確認されます。
- 未達の場合、18か月間は本補助金や他制度で大幅減点の対象(正当な理由がある場合を除く)。
👉 詳しくは第9章を参照してください。
現地調査
- 中小機構や事務局が現地調査を行い、設備や証憑を確認します。
- 確認できない費用は補助対象外となります。
財産管理・保険加入
- 単価50万円以上の設備は法定耐用年数まで処分制限あり。譲渡・廃棄・転用・貸付・担保設定には事前承認が必要。
- 導入設備には原則必ず保険または共済(付保割合50%以上)へ加入することが原則義務とされています。未加入や管理不備は取消・返還の対象です。
見積・価格妥当性
- 50万円以上の設備は原則相見積が必要。最低価格を選ばない場合は理由書と根拠資料を添付。
- システム構築費は仕様書+積算根拠が明確な見積書が必要。
リース利用時の注意
- 補助対象はファイナンス・リースのみ。
- リース料自体そのものは補助対象外で、リース料軽減計算書の提出等が必要となります。
- リース物件も処分制限の対象となります。
スケジュール管理
- 採択後2か月以内に交付申請。
- 実施期間は交付決定日から18か月以内(採択発表から最長20か月以内)。
- 工期や納期を踏まえ、期間内に完了できる現実的な計画を立ててください。
申請ルール
- 1事業者につき同一公募回での申請は1件まで。
- 親子会社など「みなし同一法人」規定に注意。
- 他補助金との経費の重複受給は禁止です。
11. よくある質問(FAQ)
本章では、申請を検討中の方からよく寄せられる質問をまとめています。
「補助金全般に共通する質問」と「新事業進出補助金ならではの質問」に分けて整理しました。
基礎的な質問(制度横断的な内容)
※ 詳しくは総合ガイドもあわせてご覧ください。
Q1. 補助金はいつ支払われますか?
A. 事業完了後に実績報告が承認されてから精算払で交付されます(前払いなし)。
Q2. 応募申請時に見積書は必要ですか?
A. 申請時は不要です。見積は採択後の交付申請で必要になります。
Q3. 交付決定前に発注・契約・支払いできますか?
A. 不可です。交付決定後の支出のみ対象です。
Q4. 支払い方法に制限はありますか?
A. 銀行振込での実績確認が必須です(現金・手形不可、クレジットは原則不可)。
Q5. 他の補助金と併用できますか?
A. 同一経費での重複受給は不可です。
Q6. 1つの公募で複数申請できますか?
A. 同一法人・事業者につき1申請のみです。
制度固有の質問
Q7. どんな経費が対象/対象外ですか?
A. 単価50万円(税抜)以上の機械装置・システム構築費を1点以上含む設備投資が必須です。
一方、パッケージ/汎用ソフト購入のみや既存システム改修・バージョンアップのみ等は対象外です。
Q8. リースで導入できますか?
A. 対象リース会社との共同申請で、ファイナンス・リースのみ可能です。
補助対象となるのは販売事業者への購入費で、リース料そのものは対象外。リース料軽減計算書の提出も必要です。
Q9. 採択後に内容を変更できますか?
A. 配分変更・中止・廃止などは必ず事前承認が必要です。
独断での変更は対象外となり、補助金返還のリスクがあります。
Q10. 採択後の義務はありますか?
A. 主な義務は以下の通りです:
- 効果報告:交付年度終了後5年間、毎年度報告が必要。未提出や未達の場合は、返還や次回申請での大幅減点の対象となります。
- 保険加入:導入設備は保険または共済(付保50%以上)に必ず加入。実績報告時に加入書類を提出します。
- 資産管理:法定耐用年数まで処分制限がかかり、譲渡・廃棄・転用には事務局の承認が必要です。違反時は残存簿価等の返還を求められます。
12. まとめ
省力化投資補助金(一般型)は、人手不足の解消と生産性向上を目的に、各社の工程に合わせた専用設計(オーダーメイド)の設備投資を後押しする制度です。
審査では、省力化効果の大きさ・投資回収の妥当性・専用設計の必然性が重視されます。補助上限も高いため、ロボットシステムなどを活用して工程を最適化したい事業者にとって有力な選択肢となります。
申請準備の第一歩
申請を検討する際は、次の準備から始めるとスムーズです:
- 主要設備リスト(単価50万円以上)の整理
- 設置計画と工程別のBefore/After工数の作成
- 投資回収シミュレーションの検討
- GビズIDプライムの早期取得
こうした基礎準備を早めに整えることで、採択に向けた「勝ち筋」が見えやすくなります。
サポートのご案内
当事務所では、本制度の活用を検討する事業者さま向けに、事業計画書作成支援や申請サポート を行っています。
こんな方におすすめです:
- 制度の詳細を知りたい
- 自社が申請対象になるか確認したい
- 事業計画書や必要書類の準備に不安がある
初回相談は無料です。
関連記事
当事務所のブログに投稿した省力化投資補助金(一般型)の関連記事はこちらへ
https://asakura-toyama.jp/tag/shoryokuka-ippan
関連リンク
本記事の執筆者
朝倉とやまコンサルティング事務所の代表・朝倉傑が本記事を執筆しました。
執筆者のプロフィールについてはこちら↓
免責
本ガイドは公開情報に基づいた概要です。最新の要件・様式・受付状況は、必ず公式サイトおよび最新の公募要領でご確認ください。内容は予告なく変更される場合があります。