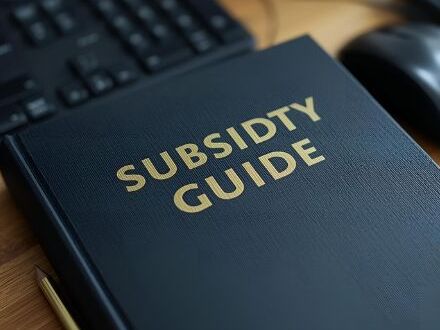「支払条件が厳しい」をパートナーシップ構築宣言で改善-手形廃止・支払サイト短縮の流れをチャンスに
はじめに:中小企業を直撃する「支払条件」の壁
中小企業にとって、日々の資金繰りは経営の最も切実な課題です。
「売上はあるのに、入金までのタイムラグで常に資金繰りに追われている」
「仕入れや投資が後手に回り、受注拡大のチャンスを逃してしまう」
こうした声は、多くの経営者から聞かれます。
とくに悩ましいのが 支払条件 です。
納品から入金まで数か月待たされる「長い支払サイト」、手形での受け取りを迫られ割引料を負担させられるケース…。こうした慣行は、資金繰りに余裕のない中小企業にとって大きな重荷となります。
幸いなことに、風向きは変わりつつあります。 近年は、国の方針により、2026年までに紙の約束手形は廃止され、電子化へ移行することが決まっています。さらに支払条件の適正化、すなわち支払サイトの短縮も強く求められるようになっています。これらの流れは、中小企業にとって資金繰り改善の追い風となり得ます。
もっとも、支払条件の改善は待っていれば自動的に実現するものではありません。発注者が支払条件の見直しに取り組み、中小企業がその取り組みに積極的に関わることで初めて恩恵を受けられるのです。
本記事では、こうした状況のなかで「支払条件が厳しい」という課題にどう向き合うべきか、そしてその解決策のひとつとなり得る パートナーシップ構築宣言 について解説していきます。
資金繰り改善の一般的な手段とその限界
「支払条件が厳しい」という課題に直面したとき、中小企業がまず検討するのは従来からある資金繰り改善の手段です。代表的なものを整理すると、次のようになります。
1. 銀行融資
資金繰りを補うもっともオーソドックスな方法です。まとまった資金を調達でき、急場をしのぐには有効です。
しかし、返済の負担が重くのしかかり、審査にも時間がかかります。借入枠がいっぱいで追加融資を受けられない、という声もよく聞かれます。
2. ファクタリング
売掛債権を買い取ってもらい、早期に現金化する方法です。入金サイトが長くても、手数料を払って現金を手にできる点は魅力です。
ただし手数料率が高めで、利益を削ってしまうというデメリットがあります。「資金繰りは助かったが、結局利益はほとんど残らなかった」というケースも少なくありません。
3. 補助金
新規事業や設備投資を後押しする制度が多数あり、採択されれば返済不要という点は大きなメリットです。ただし、審査があり、申請の手間をかけても不採択になるリスクがあります。
4. 助成金
雇用や人材育成などを対象とする制度で、要件を満たせば原則として受給できます。安定性はありますが、対象分野が限定的で、すぐに資金繰り改善に直結するケースは限られます。
これらの手段は確かに有効ですが、「支払条件が厳しい」という根本課題そのものを改善する仕組みではありません。 これらの手段により資金を補えれば日常的な資金繰りは回るかもしれませんが、売上の減少や支出の増加といった変化が起きたときには、再び同じ問題に直面しやすいのです。
次章では、この「支払条件が厳しい」という根本課題に踏み込む仕組みとして注目されている パートナーシップ構築宣言 を紹介します。
パートナーシップ構築宣言とは
「支払条件が厳しい」という課題を根本から見直す新しい仕組みが、パートナーシップ構築宣言 です。
この制度は、大企業から中小企業まで幅広い企業が「サプライチェーン全体で共存共栄を目指す」と宣言するものです。単なる理念にとどまらず、取引条件に関する具体的な改善を明文化して約束する点が大きな特徴です。
特に資金繰りに直結するのが、以下のような取り組みです。
- 支払条件の改善:現金払いの推進、支払サイトの短縮、手形依存の見直しなど
- 割引料負担の是正:手形割引料を下請け側に転嫁しない
- 透明性の向上:価格決定方法やコスト負担を明確化し、不意の資金負担を避ける
ここでポイントとなるのは、「中小企業が一方的に大企業へ要求する」ものではないということです。
発注者側にとっても、宣言を行うことには多くのメリットがあります。国の方針に沿うことで補助金や公共調達で加点評価を受けられますし、ESG・CSRの観点から社会的評価も高まるのです。さらに、取引先の中小企業が経営基盤を安定させることは、品質や納期の安定という形で発注者にも利益があります。
実際にこの制度を活用して成果を上げている事例もあります。
- 藤原製本株式会社(京都府)
製本業を営む同社では、パートナーシップ構築宣言を宣言後、自社を含めたサプライチェーン全体で 約束手形の廃止に向け、現金払いへの移行を推進しています。 (出典:【令和6年度】パートナーシップ構築宣言にかかる取組事例集) - 木田精工株式会社(大阪府)
めっき処理を中心とする製造業のこの企業も、発注先・協力会社との取り決めで 手形払いを廃止し、すべて現金払いに切り替えていると報告されています。宣言後、協力会社の負担軽減や収支計算の簡便化が実現された事例です。(出典:【令和6年度】パートナーシップ構築宣言にかかる取組事例集)
これらの事例からも分かる通り、宣言をきっかけに「手形廃止・現金払い移行」といった支払条件改善が実際に動き始めており、中小企業としても十分に現実な選択肢であると言えます。
中小企業(受注側)にとってのメリット
パートナーシップ構築宣言は、発注者が宣言する制度ですが、その効果は取引先である中小企業にも直接的に及びます。とくに「支払条件が厳しい」という課題を抱える企業にとって、資金繰りの改善につながる実効性のある仕組みです。
1. 資金繰りの安定化
- 現金払いへの移行や支払サイトの短縮によって、入金が早まり、キャッシュフローが改善します。
- 手形割引料の負担廃止により、余計なコストを削減でき、利益が残りやすくなります。
👉 「売上はあるのに現金が残らない」という悩みを解消しやすくなり、経営者が安心して日常の資金繰りを回せるようになります。
2. 前向きな経営への波及効果
- 入金サイクルが短くなれば、仕入れや投資を先行できる余力が生まれます。
- 「資金が足りないから受けられない」といった受注機会の逸失を防ぎ、売上拡大につなげられます。
👉 資金繰り改善は単なる防御策ではなく、攻めの経営を可能にする基盤になります。
まとめると、パートナーシップ構築宣言の中小企業にとってのメリットは、
- 資金繰りの安定化
- 攻めの経営につながる波及効果
に整理できます。
制度を活用することで、日々の資金繰り不安を解消するだけでなく、新たな成長に向けた一歩を踏み出せるのです。
パートナーシップ構築宣言をどう進めるか
パートナーシップ構築宣言は基本的に発注者側の企業が宣言する制度です。そのため、中小企業が単独で「宣言して資金繰りを改善する」ということはできません。では、中小企業はどう関わればよいのでしょうか。
Step 1. 取引先が宣言しているかを調べる
まずは、取引先の発注者が宣言しているかを確認しましょう。公式サイトには「登録企業リスト」が公開されており、誰でも検索できます。
発注者が既に宣言企業である場合には、以降のステップは不要です。宣言企業は支払条件の改善に動いている可能性が高いため、自社もその取り組みに積極的に関わりましょう。
Step 2. 宣言企業に働きかける
取引先がまだ宣言していない場合は、「こうした制度があり、支払条件改善にもつながる」と情報提供することが有効です。国の後押しがある制度であるため、単なるお願いではなく、制度を根拠にした建設的な対話として切り出せます。
👉 次章では、発注者側にとってのメリットを整理します。取引先を説得する際の材料として活用いただけます。
Step 3. 業界団体や商工会議所を通じて動く
Step 2で個別の企業に直接働きかけるのが難しい場合は、業界団体や商工会議所を通じて要望を出す方法もあります。
実際に、内閣府・中小企業庁「パートナーシップ構築宣言に係る取組状況及び今後の方向性について」では、自主行動計画に宣言に関する記載を既にしている業界団体が、役員企業に対し宣言を働きかけることを「今後の更なる取組」と位置付けています。したがって、業界団体の力を借りて宣言を促すことも有効なアプローチといえます。
まとめると、中小企業ができることは限られているように見えますが、
- 取引先が宣言しているかを調べる
- 取引先に働きかける(次章のヒントを活用)
- 業界団体や商工会議所を通じて動く
というステップを踏むことで、制度を資金繰り改善につなげられます。大事なのは、「支払条件の改善は国が推奨している」という事実を背景に、前向きな対話のきっかけをつくることです。
発注者側にとってのメリット:説得のための材料
中小企業が取引先にパートナーシップ構築宣言を働きかけるとき、相手にとってのメリットを示せれば、交渉を前向きに進めやすくなります。ここでは、発注者にとっての代表的なメリットを整理します。
1. 補助金申請での加点
- 発注者が宣言企業となることで、特定の補助金申請で加点評価を受けられます。
- 採択可能性が高まるため、投資計画や新規事業の推進に有利になります。
一口に補助金といっても、制度ごとにパートナーシップ構築宣言の扱いは異なります。代表的な制度の比較を以下に整理しました。
| 補助金制度 | パートナーシップ構築宣言の扱い | 参照 |
|---|---|---|
| ものづくり補助金 | 加点対象 | 第21次公募要領 |
| 新事業進出補助金 | 加点対象 | 第2回公募要領 |
| 省力化投資補助金(一般型) | 加点規定なし | 第4回公募要領 |
| 小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠) | 加点規定なし | 第18回公募要領 |
| 省力化投資補助金(カタログ型) | 加点規定なし | 公募要領(250919改訂) |
| IT導入補助金(通常枠) | 加点規定なし | IT導入補助金2025 公募要領 通常枠 |
※ここで紹介した内容は、2025年時点の最新公募要領に基づいた整理です。
ただし、補助金の加点項目は公募回や枠によって変更される可能性があるため、実際に申請する際には必ずその回の公募要領を確認してください。
各制度の情報を得たい方はこちらへ↓
2. 公共調達や大企業間取引での評価
- 政府や自治体による公共調達で、宣言企業が評価対象となるケースがあります。
- 大企業同士の取引においても、宣言の有無は「適正取引に取り組む企業」としての評価基準の一つになっています。
3. CSR・ESGへの対応
- 宣言企業は「サプライチェーン全体の共存共栄に取り組んでいる」とアピールでき、CSRやESGの観点から社会的評価を得やすくなります。
- 投資家や金融機関からの信頼を高める効果も期待できます。
4. サプライチェーンの安定
- 取引先企業の資金繰りを改善すれば、結果的に品質や納期の安定につながり、発注者自身のリスク低減になります。
- 特に人手不足や原材料高騰が続く中では、取引先を守ることが自社を守ることにつながると言えます。
中小企業(受注者)向けの補足
上記のメリットは、自社にとっての発注者だけに限定されるものではありません。例えば、自社が一次受けで取引先に発注する立場にある場合には、自ら宣言企業となることで同様のメリットを得ることができます。補助金での加点や社会的評価の向上に加え、取引先との信頼関係強化にもつながります。
ただし、宣言に基づいて取引先への支払条件を見直す場合、支払サイトの短縮や現金払いの導入により、資金繰りがタイトになる可能性があります。その結果、追加の資金調達が必要になれば、資金調達コストが増加し、実質的に利益率に影響することもあり得ます。したがって、自社の資金体力や調達手段を踏まえ、無理のない範囲で取り組むことが重要です。
さいごに
「支払条件が厳しい」という課題は、多くの中小企業にとって日々の資金繰りを圧迫する深刻な問題です。従来の資金繰り対策(融資・ファクタリング・補助金・助成金)は一時的な解決には役立ちますが、支払条件そのものを改善する仕組みではないため、根本的な解決にはつながりません。
そこで注目されるのが、パートナーシップ構築宣言です。
- 現金払いへの移行や支払サイトの短縮など、直接的に資金繰りを改善する取り組みを後押しできる
- 中小企業にとっても、仕入れや投資を前向きに進める余力が生まれる
- 発注者側にとっても補助金加点や社会的評価などのメリットがあるため、交渉のきっかけを作りやすい
つまり、パートナーシップ構築宣言は中小企業が「受け身」で悩みを抱える状況を変える一歩になり得るのです。
まずは、自社の取引先が宣言企業かどうかを確認してみましょう。
それが、資金繰り改善に向けた最初の一歩になります。
本記事の執筆者
朝倉とやまコンサルティング事務所の代表・朝倉傑が本記事を執筆しました。
執筆者のプロフィールについてはこちら↓
免責
本記事は公開情報に基づいて作成しましたが、最新の情報は、必ず公式サイトでご確認ください。内容は予告なく変更される場合があります。