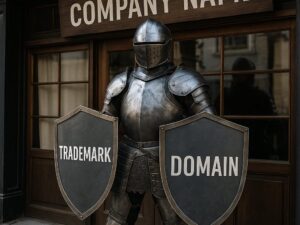補助金不正は絶対ダメ|申請者が守るべき注意点と悪質コンサルの見分け方
補助金は、本来まじめに事業に取り組む中小企業や個人事業主を支援するための制度です。
しかし近年、申請者自身が売上を偽ったり経費を水増しするケースや、悪質な補助金コンサルに丸め込まれて虚偽申請に加担させられるケースが後を絶ちません。
不正が発覚すれば、全額返還や加算金に加え、数年間の補助金申請禁止、さらには刑事事件に発展する可能性すらあります。
たとえ「コンサルに任せただけ」のつもりでも、最終的な責任は申請者本人が負うのです。
本記事では、実際の不正事例をもとに、
- 申請者が自ら不正に手を染めないための注意点
- 悪質コンサルに騙されないための見分け方と対策
を解説します。補助金を正しく活用し、事業の成長につなげるための参考にしてください。
補助金不正とは?
補助金は「本当に行った事業にかかった経費の一部を国が補助する制度」です。
したがって、実態と異なる申請や報告をすれば不正受給とみなされます。
典型的なパターンは次のとおりです:
- 対象外経費を計上する
(例:補助対象外の人件費や交際費を「対象」として申請) - 実績報告で支払額を水増しする
(例:実際は100万円の機械を購入したのに、200万円と偽った領収書を提出) - 架空の請求書や領収書を作る/改ざんする
(例:存在しない取引を捏造、領収書の日付や金額を改ざん) - 実際に導入していない設備・システムを導入したと装う
(例:補助金を受けたはずの機械やシステムが現場に存在しない)
これらはいずれも「制度の趣旨に反し、国費をだまし取る行為」と判断され、発覚すれば
返還命令・加算金・今後の申請禁止(通常3〜5年)・刑事責任 といった処分を受けるリスクがあります。
✅ ポイント
申請書の見積り段階で金額が変動すること自体はよくあることですが、実績報告で虚偽の証憑を出した瞬間に“不正”となる、という点を押さえておきましょう。
申請者自身が不正に手を染めないために
補助金はもちろん、給付金も「自己申告」に基づいて運用されます。
制度の仕組みは異なりますが、「虚偽申請は不正受給となり、返還や処分につながる」という点は共通しています。
実際、補助金では申請者自身の不正行為が公表される事例は限られていますが、給付金では大学生や個人事業主が不正に手を染めて摘発されたケースが多数報道されています。
本章では、補助金と制度上の違いがあることを踏まえつつ、参考になる給付金の不正事例を取り上げ、申請者が「自ら不正に加担しない」ための注意点を解説します。
代表的な不正事例
- 設備投資を装った不正
2022年、中小企業庁が発表した調査結果では、ものづくり補助金などで「導入したはずの設備が現場に存在しない」といったケースが報告され、交付取消や返還命令が行われています【出典:中小企業庁 公表資料】。 - 虚偽の領収書提出
実際に支払っていない経費を、偽造した領収書や改ざんした契約書で「支払ったように装う」事例も確認されています。
これは典型的な不正の手口であり、発覚すれば返還命令だけでなく刑事告発に発展する可能性があります【出典:経済産業省「補助金等適正化法に基づく不正受給処分事例」】。
解説:なぜ発覚するのか
- 補助金は実績報告時に領収書・契約書などの証憑が必須であり、監査や現地調査で確認されます。
- 「小さなごまかし」であっても、経理処理や税務申告との突き合わせで矛盾が明らかになりやすい仕組みになっています。
- 「知らなかった」「人に任せた」では済まされず、申請者本人が責任を問われるのが原則です。
対策:申請者が守るべき基本
- 経費の根拠資料を正しく保存(領収書・契約書・納品確認書など)。
- 曖昧な支出や対象外経費を「ついでに」入れない。
- 不明点は 公募要領や公式Q&Aを確認し、判断に迷う場合は商工会議所や認定支援機関へ相談する。
3. 悪質コンサルに騙されないために
補助金の申請にあたっては、専門知識や経験のある補助金コンサルに依頼すること自体は合法であり、有効に活用できる場合もあります。
しかし一部の悪質コンサル(ここでは、補助金申請支援業者だけでなく、一部のITベンダーや販売代理店など補助金の申請支援に関わる立場全般を含みます)が、
「自己負担ゼロ」「実質無料」といった甘い言葉で事業者を勧誘し、不正に巻き込む事例が後を絶ちません。
公的機関による注意喚起
補助金制度を運営する公的機関自身も、こうした不正誘導に対して繰り返し注意喚起を行っています。
- 小規模事業者持続化補助金
公式サイトでは「キャッシュバック」「キックバック」「実質無料」といった勧誘を明確に「不正行為」と記載し、事業者に注意を呼びかけています。
【出典:小規模事業者持続化補助金公式】 - IT導入補助金
中小機構の公式ページでは、「導入していないシステムを導入したと装う」「申請者以外が代理で申請を行う」といった行為をすべて不正と定義し、犯罪であると強調しています。
【出典:IT導入補助金 不正防止ページ】
実際に起きた不正事例
IT導入補助金での不正受給(2024年 会計検査院指摘)
会計検査院の調査によれば、中小企業とITベンダーが共謀し、補助金を過大請求。その後、ベンダーから「紹介料」や「キャッシュバック」として資金が申請者に還流する仕組みが多数確認されました。
ある企業では、事業費を1,500万円と偽って申請し920万円の補助金を受け取った上で、ベンダーから資金を受け取り、自己負担が実質ゼロどころか利益まで得ていたという悪質なケースも判明しています。
結果として、不正に関与した15のベンダーの登録が取り消され、企業側も補助金の返還を求められました。
【出典:日本経済新聞】
この事例が示す通り、「自己負担なし」「儲かる補助金」という勧誘は典型的な不正スキームです。申請者自身が「知らなかった」と主張しても、不正受給者として責任を問われる可能性が高いのです。
悪質コンサルの典型的な手口
| 手口 | 内容 | よくある誘い文句 | 申請者に降りかかるリスク |
|---|---|---|---|
| “実質無料”をうたう販売 | 業者が販売金額を水増しして申請し、その金額を基準に補助金が交付される。後で業者が申請者にキャッシュバックして「自己負担なし」に見せる。 | 「自己負担ゼロで導入できます」「補助金で全額カバー」 | ・補助金の資金還流は典型的な不正受給 ・返還命令+加算金、公表処分、刑事告発の可能性 |
| 代理申請・丸投げ | GビズIDや申請アカウントを渡し、業者が代理で入力 | 「手続きは全部任せてOK」「面倒なことは一切不要」 | ・申請内容を把握していなくても責任は本人 ・不正があれば返還命令・採択取消 |
| 導入していない経費を申請 | 実際には納品されていない/導入直後に解約 | 「形だけで大丈夫」「導入したことにしておきましょう」 | ・証憑が虚偽と判明すれば即不正認定 ・補助金全額返還+今後の申請資格停止 |
| 水増し申請による高額成功報酬 | コンサルが経費を大きく見せて申請額を膨らませる。実際の交付は審査で減額されるが、報酬は申請額ベースで請求される | 「補助金額を最大限引き出せます」「採択されれば成功です」 | ・補助金は減額され想定より入らない ・報酬だけ高額に請求され、結果的に赤字になる恐れ |
見分け方
悪質コンサルによる不正に巻き込まれないためには、「怪しいサインを見抜く」ことと「基本を徹底する」ことが重要です。基本の徹底については次章で、怪しいサインの見抜き方は本節で解説します。
✅ 見分け方のチェックリスト(こんな業者は要注意)
- 「自己負担ゼロ」「実質無料」など、申請者の負担がない/極端に低いと強調する
- GビズIDなどアカウント情報の提出を求めてくる(他人に貸与するのは規約違反であり、不正に加担させられる危険がある)
- 「全部任せてください」と言って申請書類を見せない
- 「面倒なことは何もしなくていい」など、申請者の手間が一切ない/極端に少ないと強調する
- 必要性の乏しい経費や補助対象外の経費を偽装して申請に含めようとする
申請者が守るべき基本的な対策
ここまで見てきたように、不正のリスクは「申請者自身の行為」だけでなく、「悪質コンサルに巻き込まれる」ことで生じる場合もあります。
しかし、最終的に責任を負うのは申請者本人です。知らないうちに不正に関わってしまったとしても、「知らなかった」では済まされません。
不正を防ぐためには、申請者自身が 基本を徹底すること が最も有効です。以下のポイントを押さえておきましょう。
契約・申請前のチェックポイント
- 契約書・見積書は必ず確認する
└ 経費の内訳(品目・数量・単価)が明確になっているか、相場から逸脱していないかをチェックする。 - 「キャッシュバック」「自己負担ゼロ」と言われたら即NG
└ 補助金の資金還流は明確な不正行為。 - GビズIDなどアカウント情報は渡さない
└ 代理申請は禁止。必ず自分でログインし、必要なら業者は画面共有でサポート。 - 申請書類は必ず自分で確認・承認する
└ 「全部任せてください」と言われても、提出前に最終版を確認し、控えを保管する。 - 必要性の乏しい経費や対象外経費は含めない
└ 公募要領を必ず読み、疑わしい場合は事務局や商工会議所に確認する。 - 業者とのやり取りは必ずメールや書面で残す
└ 口約束は避け、契約・申請時の交渉履歴を証拠として残す。
補助事業の実施期間・実績報告時の注意
- 領収書・契約書・納品書・写真などの証拠を全て保管する
- 導入した設備やソフトは実際に稼働させる
└ 導入直後に解約・返品すると「虚偽の申請」と見なされる可能性がある。 - 経費や納品に関するやり取りを文書で残す
└ 請求書、振込記録、納品報告メールなどは後の実績報告の裏付けになる。
怪しいと思ったら
- 支払いを中止し、契約内容を確認する
- メール・契約書・見積・領収書などを保存し、証拠化する
- 補助金事務局・商工会議所・認定支援機関に相談する
- 悪質な場合は、弁護士や税理士に相談し、場合によっては自主返還を検討する
相談できる公的窓口
- 補助金事務局の問い合わせ窓口
疑問点は必ず事前に確認できる。 - 商工会議所・商工会
地域の中小企業支援窓口として相談可能。 - 認定経営革新等支援機関
制度に精通した専門家が多く在籍。
さいごに 〜申請者自身が“守りの意識”を持つことが最善の対策〜
補助金は、事業者の挑戦を後押しする大切な公的資金です。
しかし一方で、不正受給が後を絶たず、摘発や返還命令、公表処分といった重いペナルティを受けた事例が相次いでいます。
本記事で紹介したように、
- 申請者自身が不正に手を染めてしまうケース
- 悪質コンサルに巻き込まれてしまうケース
の両方が存在します。いずれの場合も、最終的に責任を負うのは申請者本人であることを忘れてはいけません。
本記事でのポイント
- 不正は厳しく取り締まられており発覚するリスクが高い
- 不正に加担すれば、返還命令や加算金、将来の補助金申請資格の停止、場合によっては刑事告発といった重い代償を負う
- 悪質コンサルの甘い誘い文句に注意
- 契約や申請の段階で自分自身が主体的に確認・判断することが最善の対策
読者への呼びかけ
補助金は本来、事業の成長を後押しする強力な支援策です。
そのチャンスを不正によって失うことほどもったいないことはありません。
「手間を惜しまない」「怪しい誘いには乗らない」「書類を必ず自分で確認する」——
こうした小さな心がけが、補助金を安心して活用するための最大の武器になります。
公的資金を正しく使い、自社の成長につなげるためにも、ぜひ本記事の内容を日々の実務で意識していただければと思います。
安心して補助金を活用するために
当事務所では、補助金を正しく・安心して活用したい事業者さま向けに、
事業計画書の作成支援や申請サポートを行っています。こんな方におすすめです:
- 補助金制度を活用したいが、不正に巻き込まれるのが不安
- 自社の計画が対象になるか確認したい
- 事業計画書や必要書類の準備に不安がある
- 公的機関のチェックに耐えられる内容にしたい
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
当事務所は、補助金制度の健全な活用を支援する立場として、不正行為には一切加担いたしません。
安心してご相談いただけるよう、誠実で実効性あるサポートをお約束します。
本記事の執筆者
朝倉とやまコンサルティング事務所の代表・朝倉傑が本記事を執筆しました。
執筆者のプロフィールについてはこちら↓
免責
本記事は公開情報に基づいて作成しましたが、最新の情報は、必ず公式サイトでご確認ください。内容は予告なく変更される場合があります。