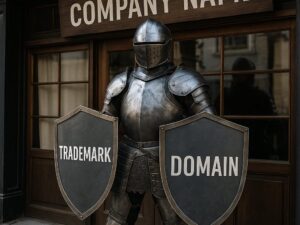中小企業の事業承継・後継者問題で失敗しないために|押さえるべきポイントと事業承継・M&A補助金の活用法
「事業承継の準備はまだ早い」と思っていませんか?
実際には、後継者が決まらずに黒字のまま廃業を選ぶ中小企業が後を絶ちません。承継は単なる世代交代ではなく、会社の未来を左右する一大プロジェクトです。
では、なぜ事業承継はうまくいかないのでしょうか。
そこには「後継者の選び方・育て方」「知的資産の承継」「従業員や取引先との信頼維持」など、人や組織に関わる課題があり、さらに「資金面や専門的知見」といった実務的なハードルも存在します。
本記事では、事業承継を失敗させないための重要なポイントと直面しがちな課題を整理し、その上で国の制度である「事業承継・M&A補助金」がどのように役立つのかをご紹介します。
中小企業の事業承継を巡る現状
日本の中小企業は、地域経済や雇用を支える重要な役割を担っています。しかし近年、経営者の高齢化が加速しており、事業承継は避けて通れない大きな経営課題となっています。中小企業庁の調査では、経営者の平均年齢は60歳を超え、70代以上の経営者も増加しています。その一方で、後継者が決まっていない企業は依然として多数存在しています。
この結果、黒字経営であっても後継者不在を理由に廃業を選ぶ企業が少なくありません。廃業は経営者本人の決断にとどまらず、従業員の雇用、取引先との関係、地域社会全体に大きな打撃を与えます。例えば、地方の老舗製造業が廃業すれば、蓄積された技術やノウハウ、長年築いた取引ネットワークが一気に失われ、地域経済のサプライチェーンにも影響が及びます。
さらに、後継者が決まっていても、承継準備が十分でないことによるリスクも大きな問題です。事業承継は単に株式や経営権を引き継ぐだけではありません。人材、技術、ブランド、顧客基盤といった「企業の強み」をどのように次世代に引き継ぐかが重要であり、その準備を怠ると、承継後に経営が不安定化してしまいます。
加えて、承継を実際に進める際には次のような実行上のハードルが立ちはだかります。
- 資金面の負担:承継後の設備更新や新規事業展開に必要な資金を確保できない。
- 専門的知見の不足:承継計画や資源の棚卸しを経営者だけで行うのは難しく、外部専門家の助言が不可欠。
- M&A後の統合リスク:第三者承継の場合、企業文化や人材の統合に失敗するリスクがある。
- 撤退コストの高さ:後継者が見つからず廃業を選んだ場合、在庫処理や人員整理などに大きな費用が発生する。
こうした背景と実行上のハードルが、中小企業の事業承継を難しくしているのです。そして、これらの課題を乗り越えるために活用できるのが、国の補助金制度です。次章では、事業承継を成功させるために経営者が押さえるべき具体的なポイントについて見ていきます。
事業承継で失敗しないために必要なこと
事業承継は「経営者交代の瞬間」ではなく、長期的に準備を進めるプロセスです。失敗を避けるために押さえるべきポイントは以下のとおりです。
後継者の選び方
まず重要なのは「誰に承継するか」を決めることです。親族内承継、従業員承継、第三者への承継(M&A)など選択肢は複数あり、それぞれにメリット・デメリットがあります。経営者の意向だけでなく、会社の将来性や従業員・取引先の受け止め方も踏まえて最適な承継先を選ぶ必要があります。
後継者の育成と社内体制づくり
後継者を選んだら、経営者としての能力を高める教育と経験の機会を意識的に設けることが大切です。顧客・金融機関・仕入先など重要な関係者との信頼関係を少しずつ築かせることが、承継後の安定につながります。また、幹部や従業員に適切なタイミングで方針を共有し、社内の理解を得ることも欠かせません。
見えにくい経営資源=知的資産の承継
事業承継では「株式や設備」といった目に見える資産の承継、例えば節税などのトピックに関心が向きがちです。これらが重要であることは確かです。しかし、経営理念、顧客や金融機関との信頼、ブランド、独自技術やノウハウといった「見えにくい資産=知的資産」もまた事業の継続性を支えていることを強く意識すべきです。
これらが引き継がれなければ、会社は承継前と同じようには機能できず、結果として事業が立ち行かなくなったり、社内外の信頼を失ったりするリスクが高まります。
ただし、知的資産は「会社を最も理解している経営者」であっても気づかない部分があり、言語化や棚卸しが難しいのが実情です。だからこそ、中小企業診断士や弁理士といった第三者専門家の助言が有効です。客観的視点を取り入れることで、漏れのない承継計画の立案や、埋もれていた知財の発見につながります。さらに、掘り起こした知財を権利化することで、会社の競争力を盤石にすることができます。
外部支援を早めに活用する
事業承継は経営者一人で抱え込むものではありません。税理士・会計士による財務面の整理、弁護士による契約関係の確認、中小企業診断士による経営資源の棚卸しなど、複数の専門家を早期に組み合わせて関与させることが、承継失敗のリスクを大幅に減らします。
実行にあたって直面する課題
事業承継は計画を立てても、実際に進める段階では多方面にわたる課題が浮き彫りになります。大きく分けると、「人・組織・心理」に関する課題と、「お金・実務」に関する課題があります。
人・組織・心理の課題
課題1. 経営者本人の心理的ハードル
事業承継を先送りする経営者は少なくありません。
- 「まだ元気だから今は考えなくてもよい」
- 「経営権を手放すのは不安」
- 「後継者に任せられるか疑問」
こうした心理的要因が準備を遅らせ、結果的に承継のタイミングを逃すことにつながります。
課題2. 後継者の資質・覚悟
承継する人材が決まっても、その人物が経営者としての覚悟や資質を備えているかどうかは大きな課題です。経験不足や社内外の信頼不足が承継後に顕在化すると、事業の安定が揺らぎます。
課題3. 従業員・取引先との信頼関係
事業承継は社内外の関係者にとって大きな転換点です。従業員に不安や不満が広がれば離職につながり、取引先が不安を感じれば取引縮小につながる可能性もあります。後継者を早めに関係者に紹介し、信頼関係を構築することが不可欠です。
お金・実務の課題
課題4. 資金面の負担
承継後には設備更新、新規事業、デジタル化・省力化投資など、将来の成長に不可欠な投資が必要となります。しかし、承継直後は資金繰りが厳しく、投資を先送りしてしまうケースも多く見られます。
課題5. 専門的知見の不足
株式・資産の承継に加え、経営理念やノウハウといった「見えにくい資源」の棚卸しも必要です。税務・法務・知財など幅広い分野を網羅するのは経営者や後継者だけでは困難で、外部専門家の関与が欠かせません。
課題6. M&A後の統合リスク
第三者承継(M&A)では、買い手と売り手の企業文化や仕組みの違いが統合を難しくします。PMI(経営統合)の失敗は、せっかくの承継を価値毀損に導くリスクがあります。
課題7. 後継者不在時の廃業コスト
後継者が見つからず廃業を選ぶ場合、従業員の雇用整理や設備処理、債務整理など大きな費用が発生します。黒字であっても「廃業コスト」を理由に撤退できず、経営者が苦悩するケースもあります。
このように、事業承継には心理的・組織的な課題から資金・専門性に関わる実務課題まで、多岐にわたるハードルがあります。もちろん、すべてを一度に解決できる特効薬のような手段があるわけではありません。特に、人・組織・心理の課題は、一筋縄ではいかないことが多いです。
一方、お金・実務の課題――特に資金面や専門家活用といった領域については、「事業承継・M&A補助金」の活用が解決の大きな後押しになり得ます。
次章では、それぞれの課題に対して事業承継・M&A補助金のどの枠が活用できるのかを整理してご紹介します。
課題解決に役立つ事業承継・M&A補助金
事業承継には前章で解説した多様な課題がありますが、資金や専門知見といった「お金・実務」の課題の解決には事業承継・M&A補助金が役立つ可能性があります。
事業承継・M&A補助金には複数の「枠」があり、それぞれ対象とする課題が異なります。以下では、前章で整理した課題と補助金枠を対応付けて紹介します。
👉 詳細や最新の公募情報は、公式サイトをご確認ください。
事業承継・M&A補助金 公式サイト
事業承継促進枠-「課題4. 資金面の負担」の解決を後押し
承継後の成長投資に必要な費用を補助する枠です。対象となる経費の例は以下の通りです。
- 老朽化した設備の更新費用(製造機械、店舗改装など)
- 新規事業や新分野展開のための投資(新しい製品ライン、販路開拓)
- デジタル化・省力化のシステム導入費(会計システム、物流管理システムなど)
承継直後でも思い切った投資ができるよう、資金面で後押しします。
専門家活用枠-「課題5.専門的知見の不足」の解決を後押し
承継計画や知的資産の棚卸しなど、専門的なアドバイスにかかる費用を補助する枠です。対象となる支援の例は以下の通りです。
- 中小企業診断士による経営資源の整理・承継計画作成支援
- 弁理士による知財の掘り起こしや権利化にかかる助言
- 税理士・会計士による資産承継・税務対策の最適化
外部専門家に依頼しやすくなり、抜け漏れのない計画策定が可能となります。
PMI推進枠-「課題6. M&A後の統合リスク」の解決を後押し
M&Aで第三者に承継した後の「統合費用」を補助する枠です。対象となる取組の例は以下の通りです。
- システムや業務フローの統合費用(基幹システムの一本化など)
- 人材定着・組織融合のための施策(人事制度整備、研修費用など)
- ブランドや事業戦略の整理・統一にかかる費用
買い手と売り手の企業文化・仕組みの違いを埋める取り組みを後押しします。
廃業・再チャレンジ枠-「課題7. 後継者不在時の廃業コスト」の解決を後押し
やむを得ず廃業を選ぶ場合の費用や、再チャレンジのための費用を補助する枠です。対象となる経費の例は以下の通りです。
- 在庫処理や設備処分にかかる費用
- 従業員の雇用整理(退職金・解雇手当等)の負担
- 廃業後の新しい挑戦に必要な経費(新規法人立ち上げや新事業の準備)
「黒字廃業」に直面する企業が次のステップに進むための支援となります。
まとめ
事業承継・M&A補助金は、資金や専門家活用といった「お金・実務の課題」を解決するための心強い制度です。一方で、「経営者本人の心理」「後継者の資質」「従業員・取引先との信頼関係」といった人・組織・心理の課題は、時間をかけた準備と関係者の理解が不可欠です。
つまり、人・組織・心理の課題には粘り強い取り組みが必要であり、資金や専門知見の課題は補助金で後押しできる。この二つを両輪として進めることが、事業承継を成功に導くカギとなります。
さいごに
中小企業にとって、事業承継は単なる経営交代ではなく、会社の未来を左右する大きな節目です。
本記事では、
- 現状とリスク(経営者の高齢化・後継者不足)
- 失敗しないためのポイント(後継者選び・育成、知的資産の承継、外部支援活用)
- 実行時に直面する課題(人・組織・心理の課題と、お金・実務の課題)
- 課題ごとに活用できる補助金の枠
を整理してきました。
事業承継に立ちはだかる課題は、経営者や後継者が時間をかけて向き合い、従業員や取引先を巻き込みながら取り組む必要があるものが多くあります。特に「人・組織・心理」に関する課題は、一朝一夕に解決できるものではありません。
一方で、「資金面の負担」や「専門的知見の不足」といった「お金・実務」の課題については、事業承継・M&A補助金を活用することで現実的な後押しを得ることができます。
つまり、人・組織・心理の課題には時間と対話、外部関係者との協力を積み重ね、お金・実務の課題は補助金を活用してリスクを軽減する。 この両輪を組み合わせることが、事業承継を「終わり」ではなく「未来への投資」に変えるための鍵となります。
事業承継は、会社の歴史を次世代へつなぐと同時に、新たな成長のスタートラインです。早めの準備と正しい情報収集、そして補助金の賢い活用で、未来への一歩を踏み出しましょう。
ご相談ください
当事務所では、顧問契約やスポットのコンサルティング、調査・分析業務、補助金申請支援などを通じて、事業承継に取り組むお客様をサポートしています。
事業承継に関する不安や課題があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
本記事の執筆者
朝倉とやまコンサルティング事務所の代表・朝倉傑が本記事を執筆しました。
執筆者のプロフィールについてはこちら↓
免責
本記事は公開情報に基づいて作成しましたが、最新の情報は、必ず公式サイトでご確認ください。内容は予告なく変更される場合があります。